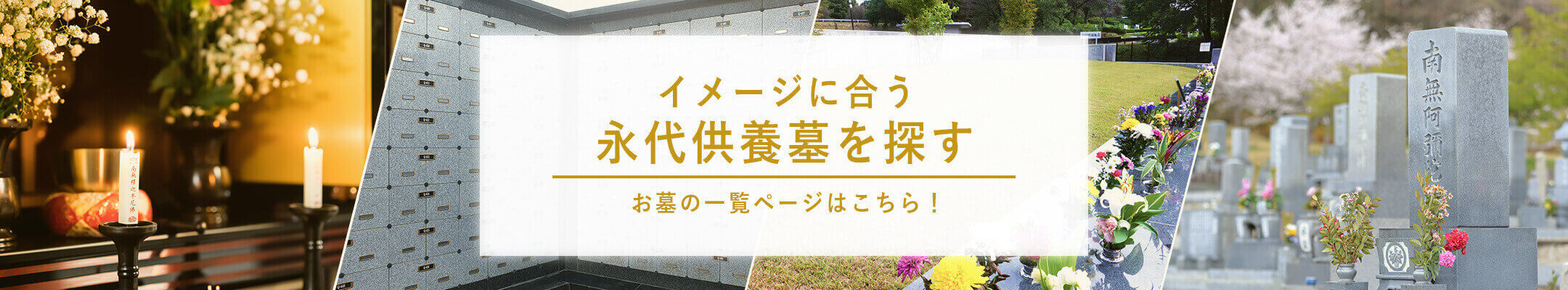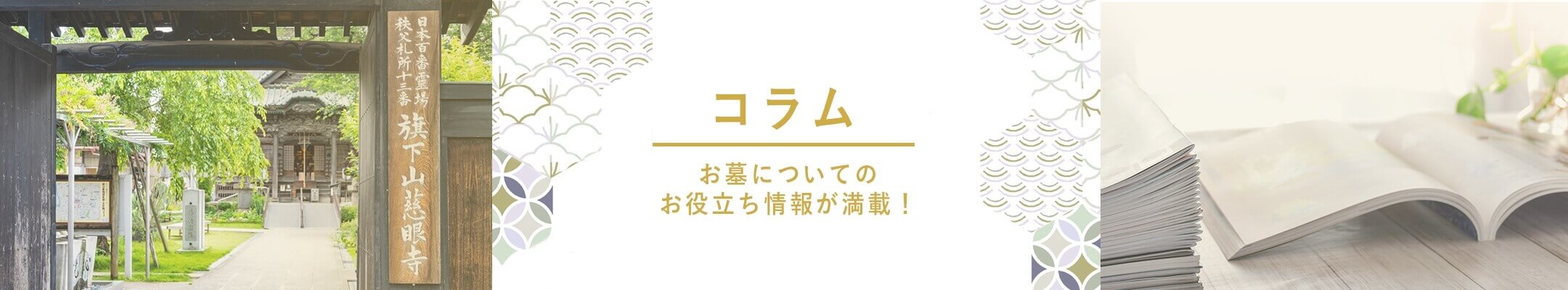永代供養でもお布施は必要なの?費用相場や渡し方も詳しく解説
永代供養とは、お墓を継いだり管理する人がいない、または様々な事情で管理や供養がむずかしい方の代わりに、お寺や霊園が代わって行ってくれる供養方法です。
そのため永代供養にすると、基本的にはご家族などの遺族が法事などを行う必要はありません。
法事がないのであればお布施を納める必要はないと考える方もいらっしゃると思いますが、場合により永代供養でもお布施が必要になることはあります。
今回のコラムでは、お布施とは何なのか、永代供養でも納めるお布施とはどんなもので、永代供養のお布施はどのくらい必要なのか、どう納めればいいのかなどを解説していきます。永代供養の費用内訳や種類についても解説するのでぜひ最後までご覧ください。
目次
お布施とは
お布施はもともと、六波羅蜜(ろくはらみつ)と呼ばれる仏教での修行に含まれるもので、人に施しを与えるという意味があります。
- 財施(ざいせ)/お金や衣服、食べ物などの施しを与えること
- 法施(ほうせ)/仏教の教えを説き、読経すること
- 無畏施(むいせ)/不安や恐怖を取り除き、人に安心感を与えること
上記の3種類のお布施に分かれますが、お葬式や法事の時にお寺の住職などにお渡しするお布施は、財施というお布施になります。
このお布施というものは、お葬式や法事での読経や、戒名の授与を行っていただいたお寺の方への報酬としてお渡しするものではなく、そのお寺のご本尊に捧げるものです。
こちらからは「お布施」という物質的な施しを、僧侶からは「読経」という形でお布施をいただいているのです。あくまでも読経に対してのお礼の気持ちを包むものなので、金額に明確な決まりはありません。
そうは言ってもどれぐらいの金額を包むべきか迷ってしまいますよね。
ここからは永代供養でどんな時にお布施が必要なのか、永代供養のお布施の費用相場はどれぐらいなのかを詳しく解説していきますね。
永代供養でお布施が必要な場面
それでは、いったい永代供養のどんな場面でお布施が必要になるのか見ていきましょう。
- 納骨法要
- 年忌法要
それは大きく分けて、納骨をする際の納骨法要のときと、一周忌、三回忌、七回忌といった年忌法要のときにお布施が必要になります。
永代供養の場合、基本的にはご家族などの遺族が法事を行う必要はありませんが、それでもやはり故人が亡くなってからの節目の年には親族で集まり、故人を偲ぶための年忌法要を行う人は多いです。
納骨法要のお布施
納骨法要とは、亡くなった方のご遺骨をお墓に納めるときに行われる法要です。
納骨をする時期ですが、これには特に決まりはなく、すでにお墓を購入していたり、先祖代々のお墓がある場合は四十九日の法要に合わせて納骨をする方が多くいらっしゃいます。
まだお墓がない場合は一周忌を目安に納骨する方が多いようですが、一年経っても気持ちの整理がつかずに納骨ができなかったり、気に入ったお墓が見つからないという方もいます。
他にも百日法要の時や、葬儀の当日や火葬してそのまますぐに納骨をしてしまうこともあります。
永代供養のお墓でも、こういった納骨の際は納骨法要を執り行いますので、そのときにはお布施をお渡しします。
永代供養の場合は、永代供養料に納骨法要のお布施などもすべて含めた金額での契約の場合もあるので確認してみましょう。
年忌法要のお布施
年忌法要とは、亡くなった方の命日から節目となる年に行われる法要です。
亡くなってから一年目が一周忌、二年目が三周忌、六年目が七回忌となります。
その後十三回忌、十七回忌と三と七がつく年に法要を行いますが、七回忌以降は規模が縮小していき家族だけで行う方も増えています。
この年忌法要の際に僧侶に読経をしてもらい、お布施をお渡しするのが一般的です。年忌法要は永代供養料に含まれていないことがほとんどなので、法要ごとにお渡しする必要があります。
近年は年忌法要を簡単に済ませるという方も増加しており、法要を簡単に済ませる場合はお布施は必要ないこともあります。
永代供養のお布施の費用はいくら?
ここでは永代供養のお布施の費用相場を見ていきましょう。
お布施は僧侶に対して読経の感謝の気持ちとしてお渡しするものなので明確な金額は決まっていません。地域や宗派によっても違いはあるでしょう。
本来お布施は「寺院のご本尊に捧げるもの」で、本尊をお守りする活動や建物の維持管理などに使われます。
具体的な金額は決まっているわけではなく、寺院も金額を重視しているわけではありません。
とは言っても大体どれくらいの金額をお渡しするべきか悩んでしまいますよね。
- 永代供養の納骨法要
- 永代供養の年忌法要
- 永代供養のその他にかかる費用
に分けて詳しく解説いたします。
納骨法要のお布施の費用相場
お礼の気持ちとしてお渡しするお布施なので決まった金額はありませんが、3〜5万円がお布施の相場と言われています。
これにお墓の魂入れをする開眼供養が必要な場合はさらに3〜5万円、開眼供養料としてのお布施が必要になることもあります。
また、四十九日と納骨式を同時に行うことも多く、その場合は四十九日の法要のお布施と合わせて5〜10万円ほど包むこともあります。
年忌法要のお布施の費用相場
一周忌、三回忌、七回忌といった年忌法要のときのお布施も、3〜5万円が相場になります。
年忌法要を寺院ではなく自宅などで行い僧侶を招く際は、御車料と御膳料が必要になります。目安はおおよそ5千円〜1万円ほどになります。
永代供養でその他にかかる費用
永代供養のお墓でも、上に述べた法要以外に費用がかかることがあります。
故人が亡くなってから四十九日(忌明け)以降に初めて迎えるお盆に行う新盆法要で、お坊さんを招いて読経をしていただく際には、3〜5万円のお布施が必要になります。
初七日やお彼岸など、僧侶に読経をしてもらう場合はお布施が必要と考えておきましょう。
また、塔婆が立てられる永代供養のお墓の場合、お盆やお彼岸のときに塔婆を立てたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。この塔婆を作る費用は3〜5千円かかります。
永代供養のお布施の書き方は?
いざ永代供養のお布施を用意するとなると「どうやって書いたらいいの?」「何を用意すれば良いの?」と悩んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
永代供養のお布施の封筒の書き方や、封筒の選び方を詳しく解説していきますね。
永代供養のお布施はどんな封筒に入れたら良い?
永代供養でお布施をお渡しするとき、できるだけ郵便番号の枠などが書かれていない、何も印札されていない白無地の封筒に入れると良いでしょう。水引などが印刷されている封筒を使う場合は、白黒や黄色のインクで印刷されたものにします。
永代供養のお布施の表書き
永代供養のお布施を入れる封筒の表書きには「お布施」または「御布施」と書いておきます。
既に「お布施」と印刷されているものを使っても構いません。
中央の下段には「〇〇家」と姓を記入、または代表者の氏名を書きましょう。
濃墨を使用して毛筆、または筆ペンで書きましょう。
永代供養のお布施の裏書き
永代供養の封筒の裏面には住所、氏名、金額を書きます。
裏面を記入する際はお布施の金額の書き方が重要になってきます。金額は「金〇〇圓也」と書き、漢数字は「壱、弍、参」のように旧字体で書きましょう。
永代供養のお布施は新札でもいいの?
お葬式などの香典としてお渡しする場合、不幸が起こることを準備していたという意味があるとして新札を使わないことが一般的なマナーになっています。
しかし永代供養のお布施は香典ではありませんので、新札を使っても問題ありません。
浄土真宗のお布施の書き方は?
浄土真宗は「亡くなってすぐに成仏できる」という教えから永代供養という概念がなく、永代供養ができないとお考えの方もいるようです。
しかし近年では永代供養墓を利用する人の増加に合わせて、永代供養に対応している浄土真宗の寺院も増えてきました。
浄土真宗のお布施の表書きは、仏教の教えを子孫にまで託すという意味で「永代経懇志(えいたいきょうこんし)」と書きます。
こちらの記事では永代供養料の封筒の書き方、お布施との違いについて詳しく解説しているので興味のある方はぜひご覧くださいね。
永代供養料の封筒の書き方は?表書きからお布施との違いまで解説
永代供養のお布施を渡すマナーとは
永代供養のお布施はいつ渡す?
お布施はいつ渡さなければいけないといった決まりはありませんが、できれば法要が始まる前がいいでしょう。住職や僧侶にご挨拶に行くときに、「本日はどうぞよろしくお願いいたします。」と挨拶をしてお渡ししましょう。
もし時間がない場合は法要が終わってからでも構いません。「本日はありがとうございました。」と一言添えてお渡ししましょう。
合同法要など人が多く集まり、住職に挨拶をする機会がない場合は受付でお渡ししましょう。
お布施の渡し方
永代供養のお布施を手渡しをする場合は、封筒のままお渡しすることは失礼に当たるので注意しましょう。
切手盆と呼ばれる黒いお盆の上に封筒をのせてお渡しします。その際に「お布施」という文字が相手から見て正面になるようにしてくださいね。
切手盆がない場合は袱紗にのせてお渡しします。
もし切手盆も袱紗もないという場合はどうしたら良い?と思った方もいるのではないでしょうか。必ずしもないとダメだというわけではないので、そういった時はしっかりと感謝の気持ちを込めてお渡しするようにしましょう。
直前に慌てないためにも切手盆や袱紗は事前に用意しておくと安心ですね。
お布施の支払い方法を確認しておく
お布施は従来手渡しが基本でしたが、最近では金額が高額なこともあり銀行振り込みを行う寺院も増えてきました。
手渡しなのか振り込みなのか、事前に確認しておくようにしましょう。
永代供養の費用内訳は?
永代供養にかかる費用の内訳は以下のようになります。
- 永代供養料
- お布施
- 刻字料
- その他の費用
永代供養料
寺院や霊園に永代にわたり管理、供養を行ってもらうための費用です。遺骨を納めるためのスペースの使用料も含まれています。
お布施
納骨法要や年忌法要の際に僧侶に読経をしてもらったときにお渡しする費用です。納骨法要のお布施は永代供養料に含まれていることもあるので確認しておきましょう。
刻字料
墓誌に故人の名前を彫刻してもらう費用です。相場は大体3万円ほどになります。
その他
その他にかかる費用としては、永代供養墓の年間管理費や墓石を建てる際の墓石代です。これらは霊園や永代供養墓の種類によって必要ないことも多いので、契約の際にしっかりと確認しておきましょう。
永代供養墓の費用の相場とは
ひとくちに永代供養墓といっても種類は様々です。かかる金額も大きく変わってくるので確認しておきましょう。
- 合祀墓
- 集合墓
- 個別墓
- 納骨堂
合祀墓
他の方のご遺骨と一緒に埋葬する方法です。費用相場は5万円〜10万円ほどと一番費用が安い形のお墓です。
集合墓
ご遺骨は個々に分けられていますが、墓標を他の方と共有するお墓です。費用相場はおおよそ20万円前後で、個別に安置される期間が決められており大抵は一定期間を過ぎると合祀墓にうつされます。
個別墓
通常のお墓と同様に個人の区画を設けたお墓です。期間を過ぎると合祀墓にうつされる場合と、永代にわたり個別に埋葬されるタイプと様々です。
費用相場は50万円〜150万円ほどと最も高くなります。
納骨堂
室内型の施設が多く、都心部や駅から近い場所に多くみられます。集合型のマンションタイプのお墓、個別のお墓を持てるものと様々で、費用相場も50万円〜150万円ほどとなります。
こちらのコラムでは永代供養墓の費用相場について詳しく解説しているので合わせて参考にしてくださいね。
永代供養は本当に安い?費用相場と予算別に安い永代供養墓を紹介
まとめ
永代供養のお墓は基本的に、供養全体のことをお寺や霊園にまかせることができ、費用も抑えられる安心できるお墓のスタイルです。
ですが、それでも遺族や親族がいる限りできるだけお墓参りも含め、故人を偲んでの法要を執り行うことも大切ですね。
今回はそういった場合に納めるお布施のことについて解説をしました。金額については個人の気持ちであったり、お寺や霊園によって様々ですので、不安に思う方は思い切って直接聞いてみることをおすすめします。何も恥ずかしいことではありません。きっと親切に教えていただけると思いますよ。
永代供養にかかるお金に関する他のコラムはこちら↓
永代供養の費用って誰が払うの?
墓じまいして永代供養墓に引っ越しする方法と費用を徹底解説