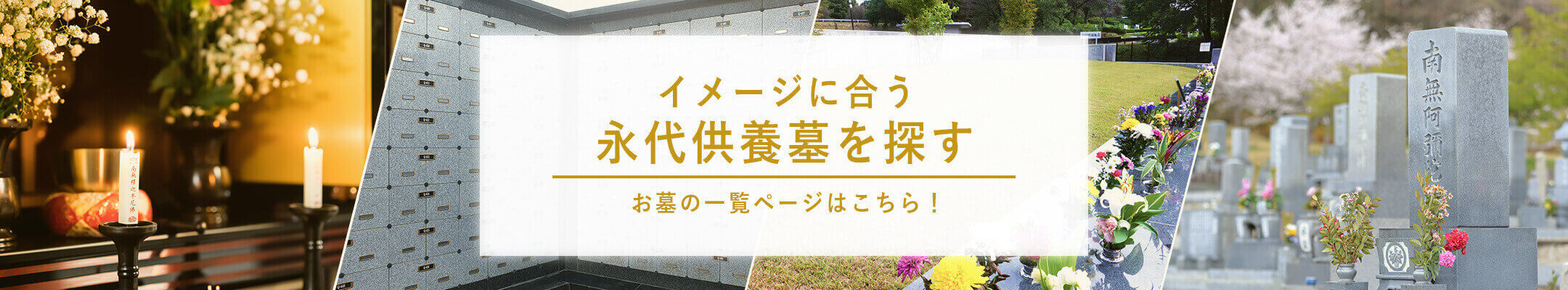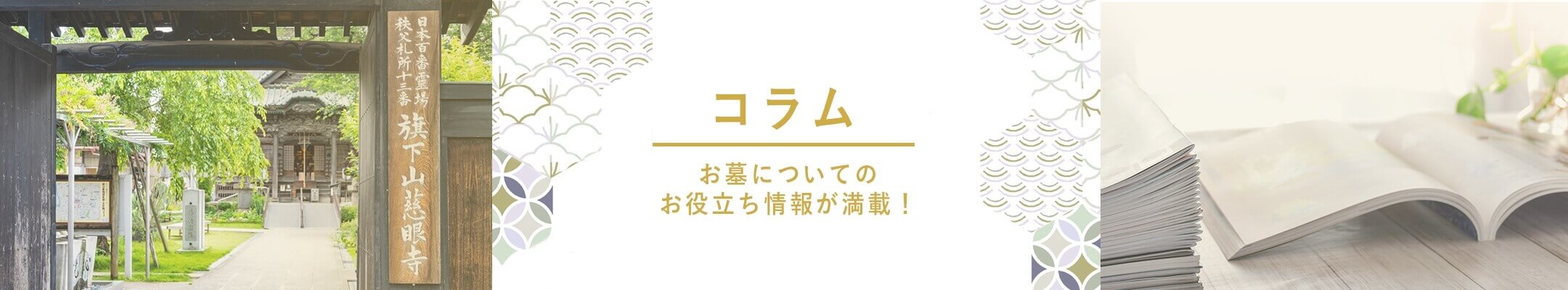【墓じまいのやり方】具体的な流れから手続きと費用までを解説!

また「もっと近くにお墓があれば管理しやすい」という理由でアクセスのよい場所にお墓を移す方もいます。しかし、いざとなると墓じまいのやり方が分からない人も多いのではないでしょうか。
|
この記事では、墓じまいをするときに出てくる様々な手続きのやり方や費用について解説しています。それではさっそく見ていきましょう。
墓じまいのやり方の具体的な流れ
墓じまいのやり方は以下のような流れが一般的です。まず何から始めたらよいのか、やり方を順番に解説していきますね。
|
墓じまいの手順 墓じまいのやり方①親族に承諾を得る 墓じまいのやり方②現在お墓のある墓地や霊園へ伝える 墓じまいのやり方③遺骨の新しい納骨先を決める 墓じまいのやり方④墓石の撤去をお願いする業者を決める 墓じまいのやり方⑤役場で必要な手続きを済ませる 墓じまいのやり方⑥閉眼供養をして遺骨を取りだす 墓じまいのやり方⑦業者に墓石を撤去してもらい更地にする 墓じまいのやり方⑧遺骨を新しい納骨先へ納める |
墓じまいのやり方①親族の承諾を得る
まず墓じまいのやり方として一番最初にしてほしいのは、親族に承諾を得ることです。
自分でよかれと思って墓じまいをしたら、あとで親族とトラブルになってしまったという話は意外に多いものです。
先祖代々続くお墓の場合など、勝手に墓じまいをすすめないで必ず親族へ相談してからにしましょう。
「死んだらそのお墓に入るつもりだった」、「お墓参りが心の癒しになっているのに」などお墓を心のよりどころとしている親族もいることを忘れないようにすると良いですね。
状況をよく説明し、墓じまいに対して理解を得られるよう努めましょう。
また、金銭面についてもトラブルが多いので、墓じまいにかかる費用の分担などについても話し合っておいた方が良いでしょう。
墓じまいのやり方②現在お墓のある墓地や霊園へ伝える
墓じまいのやり方として次にしなければならないことは、現在お墓が建っている霊園や寺院へ墓じまいの旨を伝えることです。
市や組合が管理する公営の霊園であれば墓じまいのことを伝えるだけで良いのですが、寺院にお墓がある場合は、檀家の関係もあるため少し難しい場合があります。
墓じまいするということは檀家を抜けるということになり、お寺の財政にも関係してくるため、離檀を渋ることもあると考えられます。
すんなりと話が進めばいいのですが、中にはこじれてしまうこともあるので、寺院の場合は早めに墓じまいの相談をしておいた方が良いでしょう。
寺院側に感謝の気持ちと共にしっかりと墓じまいの理由を伝え、誠意をもってお話すると良いですね。
寺院の場合は離檀料が必要になることも承知しておきましょう。現在お墓のある霊園や寺院には「埋葬証明書」を発行してもらいます。
墓じまいのやり方③遺骨の新しい納骨先を決める
墓じまいのやり方3番目は遺骨の新しい納骨先を決めなければなりません。
最近では、墓石など形のあるものを後に残したくないと考える人も多く、樹木葬や散骨などの自然葬や永代供養墓への納骨が人気となっています。
墓じまいには主に以下のような納骨先があります。
|
一般墓 |
自宅近くなど、お参りしやすい場所へお墓を引っ越しさせる |
|
合祀墓 |
他の人の遺骨と一緒に共同墓へ納骨する |
|
納骨堂 |
お堂の中に個別で厨子や棚などがあり、そこへ納骨する |
|
樹木葬 |
樹木を墓石の代わりとして木の根元または周辺に遺骨を埋葬する |
|
散骨 |
遺骨をパウダー状にして海、山、空などへ散骨する |
|
手元供養 |
お墓ではなく、自宅で遺骨を保管する |
|
永代供養墓 |
霊園や寺院にお墓の管理を一任する |
一般墓や納骨堂、樹木葬なども永代供養になっているものがありますので、よく調べてから決めるといいですね。
墓じまいしたあとは手元供養もありますが、いずれその家の方が亡くなったとき、遺骨をどうするのかという問題が出てきます。そこもよく踏まえて考えておきましょう。
永代供養はある一定の期間が過ぎると、合祀墓に埋葬されるようになっているところが多いのでよく確認することが大切です。
詳しくはこちら⇒ みんなの永代供養
遺骨の受け入れ先を決めて契約したら、納骨先の管理者に「受け入れ証明書」を発行してもらいます。納骨先が決まってもすぐに納骨できない場合もあります。
納骨できるまでに1ヶ月~2ヶ月もの期間が必要になることもあるので、墓じまいの連絡を霊園や寺院にした時点で並行して納骨先を決めておくとよいでしょう。
墓じまいのやり方④墓石の撤去をお願いする業者を決める
墓じまいのやり方4番目は墓石を撤去する石材店や専門業者に依頼をします。
霊園や寺院へ墓じまいの連絡をしたときに、指定の石材店や撤去業者の案内がある場合もあるので確認してみましょう。指定されたところがない場合は、いくつかの石材店や専門業者さんに見積もりを出してもらい、その中から選ぶと良いでしょう。
墓石の撤去は費用もかかるので実際に現地へ出向いてお墓を見てもらい、見積もりの詳細を出してもらうようにします。
墓じまいのやり方⑤役場で必要な手続きを済ませる
墓じまいのやり方5番目は役場で必要な手続きをすることです。法律で墓じまいは勝手に行なうことはできず、以下の3つの書類が必要となります。
|
・現在お墓のある墓地や寺院の管理者に発行してもらう「埋葬証明書」 ・新しい納骨先の管理者に発行してもらう「受け入れ証明書」 ・現在お墓のある自治体で発行してもらう「改葬許可証」 |
「改葬許可証」は「改葬許可申請書」を役場に提出するともらうことが出来ます。役場へ出向いていくか、役場のHPなどでダウンロードすることも可能です。
改葬許可申請書は遺骨1体につき1枚申請となっていますので、お墓に入っている遺骨が何体分あるのか確認しておくといいですね。
申請書の記載内容は、各自治体によって違います。
あらかじめ故人の『本籍地』『死亡年月日』『火葬した場所と日時』『改葬の理由』『納骨先』などの情報をまとめておくと申請がスムーズにいくでしょう。
このような手続きの時は墓じまいに関係なく、「身分証明書」が必要になることが多いので、運転免許証、マイナンバーカード、保険証などをお忘れなく。
最後に現在お墓のある霊園や寺院の管理者に署名と捺印をもらい役場に提出します。
墓じまいのやり方⑥閉眼供養をして遺骨を取り出す
墓じまいのやり方6番目は閉眼供養をしてお墓から遺骨を取り出します。
閉眼供養とは「魂抜き」、「性根抜き」とも言われており、お墓に宿る故人の魂を抜く儀礼です。
寺院にお墓のある場合はそこのご住職に、公営の墓地であれば信仰のある宗派のお坊さんにお願いするか、近くの寺院のご住職にお願いして閉眼供養をしてもらうと良いでしょう。
これによってお墓がただの墓石となり、遺骨を取り出すことが出来ます。
遺骨を取り出すやり方は、墓石撤去のときに石材屋さん、または撤去業者さんに取り出してもらうことも可能です。
閉眼供養は特にしないといけない訳ではありませんが、やはりご先祖様を敬う形として閉眼供養を行なった方が心の整理もつき、気持ちがすっきりした感じがします。
遺骨の取り出しには「改葬許可書」が必要となります。
墓じまいのやり方⑦業者に墓石を撤去してもらい更地にする
墓じまいのやり方7番目は、いよいよ墓石の撤去です。
閉眼供養が終わり遺骨を取り出したら、お願いしておいた石材屋さんまたは撤去業者さんに墓石を撤去してもらいます。
撤去した後はきれいに更地にして霊園または寺院に返還し、墓じまいは完了となります。
基礎の部分もきちんと撤去してあるのか、きれいに更地になっているのか確認するためにも、当日は立ち合いをして作業を確認しておいた方が良いでしょう。
墓じまいのやり方⑧遺骨を新しい納骨先に納める
墓じまいのやり方8番目は、取り出した遺骨を新しい納骨先へ納めます。納骨の時に「改葬許可証」が必要となります。
ここまでが墓じまいのやり方一連の手順となります。時間はかかりますが順番にすすめていきましょう。
墓じまいのやり方「服装と必要な持ち物」
墓じまいはどのような服装でいくのが良いのでしょうか。また、必要な持ち物は何があるのでしょうか。
ここでは墓じまいのやり方・「服装と持ち物編」ということで説明していきます。
墓じまいのやり方・服装
墓じまいのやり方として、服装は喪服でかまいません。喪服とまではいかなくても略喪服といわれるものでも良いでしょう。
|
●男性 : 暗い色の黒やダークグレーのスーツ ●女性 : グレーや紺色などのワンピースやスーツなど |
墓じまいのやり方・持ち物
持ち物は以下の物を持っていくと良いでしょう。
|
●ろうそく ●お線香 ●花 ●水 ●マッチやライター ●掃除道具 ●お布施 |
水や掃除道具などは霊園や寺院の方にある場合が多いですが、ない場合は持っていきましょう。
お布施も忘れないように気をつけましょう!
墓じまいにかかる費用
ここからは墓じまいにかかる費用についてお伝えしていきます。以下のようなことに費用が必要となってきます。
|
墓石の撤去作業の費用 |
10万円~15万円程度 |
|
墓じまいに必要な書類の手続き費用 |
200円~1,500円程度 |
|
閉眼供養のお布施やお礼 |
3万円~10万円程度 |
|
寺院の離檀料 |
2万円~20万円程度 |
|
遺骨の手入れ |
洗浄:1体10,000円 ~ 粉骨:20,000円~ |
|
新しい納骨先へ遺骨を納める費用 |
30万~300万円程度 |
|
合計 |
約45万~350万円程度 |
ざっくりとですが以上のような費用の計算になります。
墓石の撤去作業の費用
墓じまいの中でも費用がかかるのが墓石の撤去です。
平均的な金額としては、1平方メートルあたり10万円~15万円ほどかかります。これはお墓の立地条件でも墓石の撤去のやり方が変わってきます。
|
・霊園の通路などが狭く、お墓の近くまで重機が入れない ・お墓の区画が広い ・いくつも墓石が建っている ・遺骨の数が複数だった ・お墓が建っている場所が険しく、作業員の人数が増えた |
以上のような場合、墓石の撤去費用は高くなってきます。
墓じまいに必要な書類の手続き費用
墓じまいに必要な書類「埋葬証明書」、「受け入れ証明書」、「改葬許可証」の費用で、おもに書類作成の手数料等になります。
閉眼供養のお布施やお礼
閉眼供養の時にお坊さんに渡すお布施やお礼の金額となります。通常の法要と同額くらいが相場のようです。
あくまでも目安で、金額は決まっていないため、分からないときはご住職に直接聞いてみると良いでしょう。
寺院の離檀料
寺院にお墓があった場合は墓じまいするときに檀家から抜けることになります。この場合は離檀料を支払うのが一般的です。
今までお墓を守っていただいたお礼の気持ちとして寺院へ納めます。離檀料をとらない寺院もあれば、離檀料が一律で決まっている寺院もあるようです。
金額が決まっている訳ではなく、お礼の気持ちを込めてお渡しするものですが、まれにトラブルになり高額な離檀料を請求される場合があります。
ご住職に墓じまいしたいことを早めに伝え、感謝の気持ちを込めてお話をしていくようにしましょう。
一方的に話をせず、おだやかに墓じまいの話を進めることができるといいですね。
遺骨の手入れ、洗浄などの費用
長い年月お墓に収められていた遺骨は骨壺に水が入っていたり、湿気をおびたりして傷んでいることがあります。
中にはカビが生えて黒ずんでしまっている遺骨もあります。その場合は遺骨を洗浄したり乾燥させるなどの手入れをしなくてはなりません。しかし、勝手に水道で水を流しながら洗ってしまうと遺骨は細かく砕けてしまい、排水溝などへ流れ出てしまいます。遺骨のお手入れのやり方は難しいため専門の業者さんにお任せした方が安心です。
また、散骨を考えている場合には粉骨をしてくれる業者さんもあります。
専門業者にお願いする場合は、洗浄が1体1万円程度、粉骨が1体2万円程度となっています。
新しい納骨先へ遺骨を納める費用
納骨先にもよりますが、一般墓だと費用は高めで120万~300万程、納骨堂は30万~、樹木葬は25万~が相場となっています。
一般墓だと、お性根入れなどの費用もかかってくるでしょう。
まとめ
ここまで「【墓じまいのやり方】具体的な流れから手続きと費用までを解説!」と題しましてお送りしてきました。
今後も少子高齢化や核家族化など、墓じまいをする人は増えていくように思われます。
墓じまいの手続きのやり方は
やり方①親族で話し合い承諾を得る
やり方②霊園や寺院に墓じまいの連絡
やり方③新しい納骨先を決める
やり方④墓石を撤去する業者決め
やり方⑤役場での手続きを済ませる
やり方⑥閉眼供養・遺骨取出し
やり方⑦墓石の撤去
やり方⑧遺骨を新しい納骨先へ
ご先祖様から受け継いだ大切なお墓だからこそ、後悔しないような墓じまいをしたいですね。
この記事が少しでも皆様のお役に立てたら嬉しいです。最後までお読みいただきましてありがとうございました。