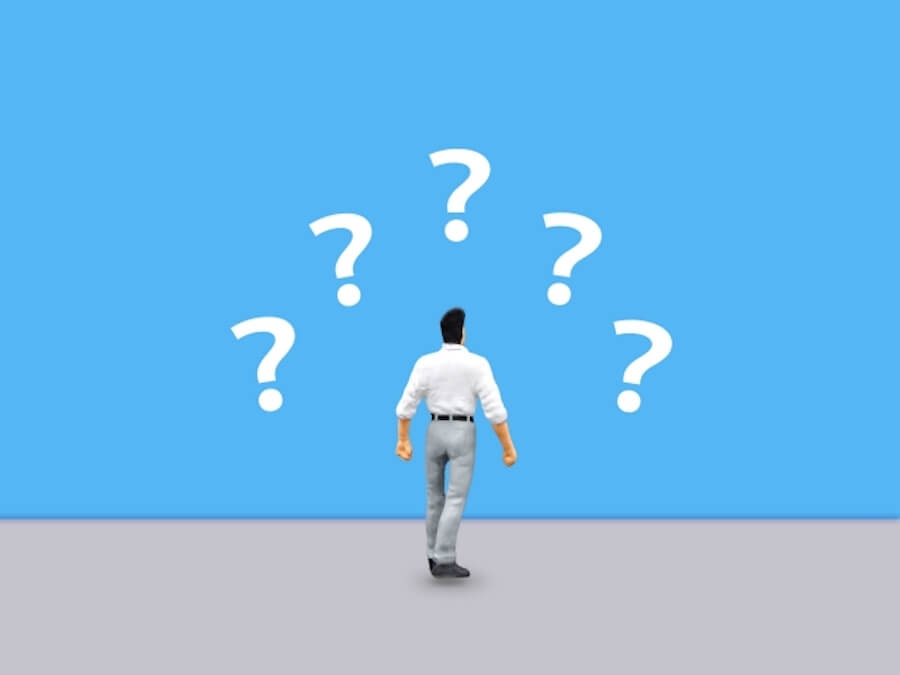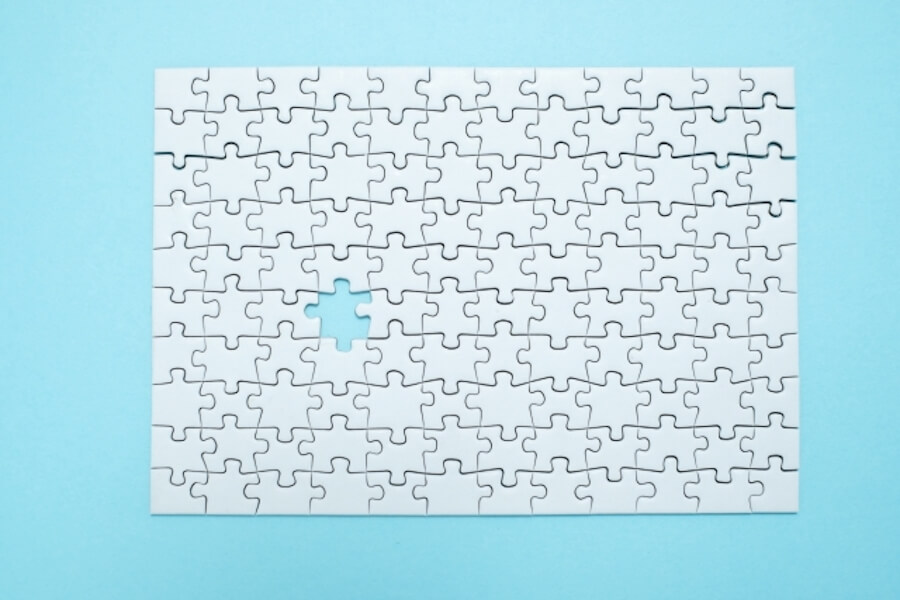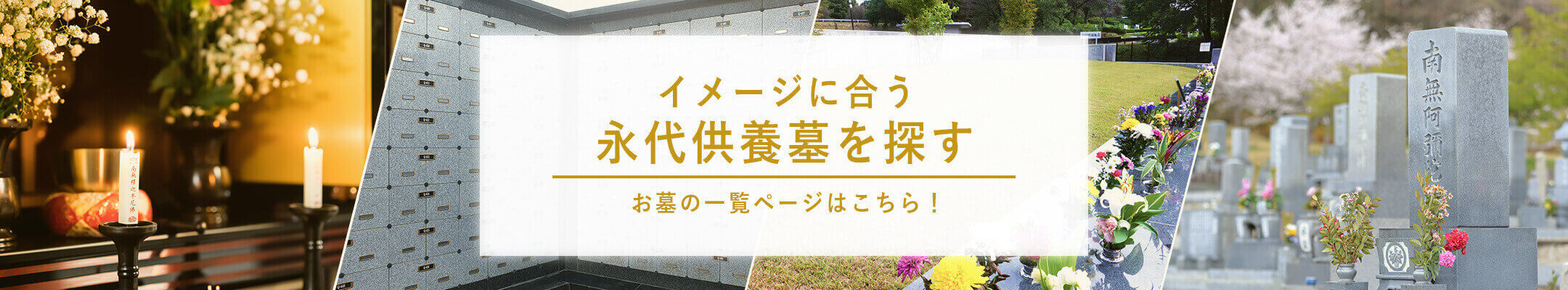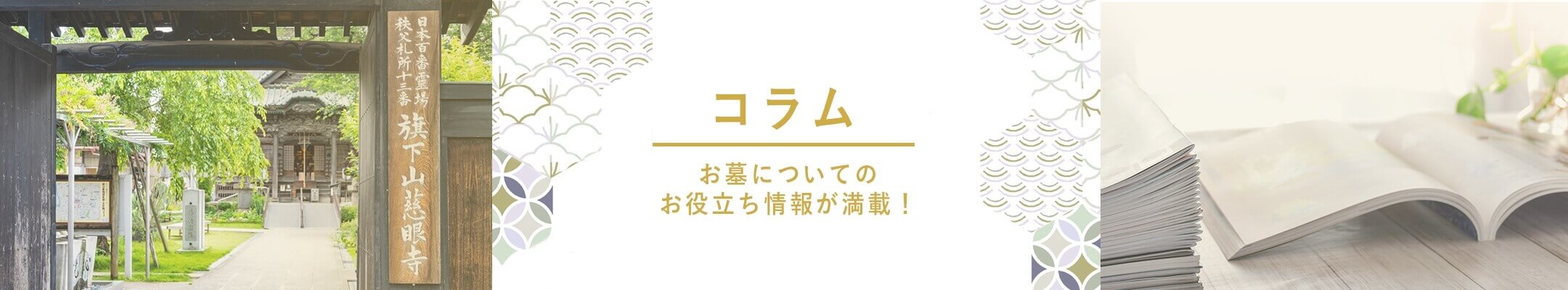永代供養したその後にある疑問は?悩みのアレコレをまるごと解説
永代供養付きのお墓を購入しようと考えているものの、
「永代供養したその後は永遠に供養してもらえるの?」
「永代供養したその後、遺骨はずっと同じ場所に置いておけるの?」
「永代供養したその後の法事は必要?」
といった永代供養をしたその後のことに疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。
永代供養は供養をおこなったその後のお墓を寺院や霊園が永代にわたり管理・供養してくれるもので、生涯独身の人や子どもがいない夫婦、子どもに面倒をかけたくないなどで承継不要のお墓を希望している方にとっては大変メリットのある供養方法と言えます。
とはいえ永代供養のその後についてよくわからない状態では、なかなか購入に踏み切れないという気持ちもあるのではないでしょうか。
安心して永代供養付きのお墓を購入・利用するためには、永代供養したその後のことを理解しておくことは必要不可欠。
そこでこちらの記事では、永代供養したその後についての疑問をまるごと解決するために、「永代供養したその後」について徹底解説しています。
永代供養付きのお墓を購入したいけどその後のことが心配で悩んでいる方や、すでに永代供養付きのお墓を購入したものの、その後のことで悩んでいるという方は、ぜひ参考にご覧ください。
目次
永代供養その後の供養は永遠にしてもらえる?
永代供養をしてもらったその後は「永代」の供養だから「永遠に供養してもらえるのよね?」と疑問に思われる方がいるのではないでしょうか。
永代供養をしたその後の供養は以下のようになります。
- お寺がある限り永遠に供養してもらえる
- 個別供養は期限があるが延長できる場合も
個別に供養する期間は寺院や霊園によって違いがありますので、しっかり確認するようにしましょう。
寺院や霊園がある限り永遠に供養してもらえる
永代供養付のお墓で供養したその後は、寺院や霊園がある限り永遠に供養してもらえます。
しかし永代供養をした寺院や霊園が、倒産や閉鎖に追い込まれるケースがないとは言えません。
特に近年は檀家離れが進み、寺院経営を継続するのが難しいことも話題になっています。※1
万が一お墓を購入した寺院や霊園が倒産したり閉鎖したりしても、その後にお墓を移動する場合は都道府県知事の許可が必要になりますので、強制的にお墓を移動することはできません。※2
とはいえこの場合、経営者が変わることで使用料や管理費などが値上げされる可能性が考えられます。
そのため永代供養付のお墓を購入する場合は、購入する寺院や霊園の人気の有無や管理状態をしっかりと確認することが大切です。
※1参考資料:文化庁宗務課・宗務寺報「1 寺院消滅時代」
※2参考資料:厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」
個別供養は期限があるが延長できる場合も
永代供養付きのお墓は、個別供養期間があらかじめ決められていることがほとんどです。
回忌に合わせて個別供養期間が終了するケースが多いのですが、いつまでの期間なのかは寺院や霊園によって異なります。
複数人が一緒に入る永代供養の場合は、最後に亡くなった方の遺骨が納骨されたその後、決められた年数を個別供養されるのが一般的です。
回忌の他にも5年や10年の期間で決められているケースもありますが、期間終了したその後も延長できる場合がありますので、事前に寺院や霊園に確認しておきましょう。
また購入時に個別供養期間を決めるのではなく、無縁になったその後、一定期間が経過したら個別供養期間を終了する永代供養もあります。
永代供養付きのお墓を購入する場合は、どの個別供養期間がご自身の希望に沿っているのかを考えて決めることが重要です。
永代供養その後の遺骨は合祀される?
永代供養のその後、遺骨がどのタイミングで合祀されるのか気になる方は多いのではないでしょうか。
永代供養したその後の遺骨を合祀するタイミングは以下のとおりです。
- 初めから合祀される
- 個別供養の期間終了後に合祀される
- 合祀されない永代供養もある
永代供養をしたその後は最終的に「合祀」されることが一般的です。合祀とは骨壺などから遺骨を出し、他の方の遺骨と一緒に埋葬することを言います。
初めから合祀される
永代供養付きのお墓を購入するときに初めから合祀墓を選択した場合は、遺骨は初めから合祀墓と言われる大きなお墓の中に埋葬し供養されます。
血のつながりなどが何もない方など全くの他人と一緒に埋葬されますが、その分他の永代供養付きのお墓よりも費用がかからないというメリットがあります。
個別供養の期間終了後に合祀される
個別供養期間がある永代供養付きのお墓を購入した場合は、個別供養の期間終了後に遺骨を合祀墓に移動・埋葬し、その後は合祀墓で永代供養されます。
永代供養の期間は購入する時にあらかじめ決められていることが一般的ですが、寺院や霊園によっては遺族の希望がある限りずっと、または決められた年数のみ延長可能な場合もあります。
親族が個別供養期間の延長を望む場合もありますので、事前にその後の延長が可能かどうかを確認しておくと安心です。
合祀されない永代供養もある
永代供養付きのお墓の中には永代供養されたその後、ずっと合祀されないお墓もあります。
近年は永代供養付きのお墓の人気があるものの、個別供養期限が過ぎたその後に「合祀されることに抵抗を感じる」という方は多くいます。
そんなニーズに応えるべく、寺院や霊園のある限りは永遠に個別供養をするという永代供養も増えています。
永代供養その後遺骨を置く場所が不足したら?
永代供養付のお墓を購入するときには何名の骨壺を置く予定なのかを考えてお墓の大きさを決めます。しかし、購入したその後に予定よりも納骨したい遺骨が多くなってしまうことが無いとは言えません。
もしも永代供養をしたその後に遺骨を置く場所が不足したら、以下の方法で納骨できるようにします。
- 古い遺骨を合祀墓に移す
- 粉骨する
- 骨壺から納骨袋に移す
それぞれ解説していきます。
古い遺骨を合祀墓に移す
永代供養をしたその後、一緒に入る予定の方の遺骨が入らなくなった場会には、先に納骨されていた古い遺骨を合祀墓に移すことがあります。
永代供養付きのお墓は納骨できるスペースが限られていることも多く、予定よりも多くの遺骨を安置しようとする場合は、すでにある遺骨を移動するなどしてスペースを確保しなければなりません。
そのため古い遺骨を合祀墓に移動し、他の方の遺骨を置けるようにします。
ただし合祀墓に移動したその後に遺骨を取り出そうとしても、一度合祀した遺骨を取り出すことはできません。
個別供養期間が終了したその後に、できるだけ近くにまとめて埋葬したいと思ってもできませんので注意しましょう。
粉骨する
遺骨を置く場所が不足した時には、遺骨を粉骨する場合があります。
粉骨とは遺骨をくだいて粉状にすることですが、こうすることで保管するスペースを大幅に縮小することができるメリットがあります。
ただしお骨を粉々にする行為に抵抗を感じる方も少なからずいますので、粉骨する場合は他の親族などとも相談する方が良いでしょう。
骨壺から納骨袋に移す
納骨袋とは遺骨を入れて保管する専用の袋で、湿気などによりカビが生えるのを防いでくれます。
骨壺だと遺骨を置くスペースを多く使いますが、納骨袋を利用すれば限りあるスペースを有効的に利用することができますので、追加で遺骨を置くことが可能になります。
永代供養その後の管理に費用はかかる?
永代供養をしたその後のお墓を管理する費用については以下のように分けられます。
- 年間管理費がかかる
- 管理費は契約時一括払い
- 管理費は不要
永代供養付きのお墓の場合、お墓の管理や供養は寺院や霊園がおこなってくれますが、そのための管理費用がかかるのかどうかを解説していきます。
年間管理費がかかる
年間管理費がかかる永代供養付きのお墓の場合は、年に1回、年間管理費を支払います。
基本的には引き落としにより支払うことになっていますが、年に1回の引き落としなので忘れてしまうことがあるかもしれません。
引き落としができなかったその後に連絡が取れなかったり、数年に渡って年間管理費が支払われなかったりした場合、個別供養のお墓から合祀墓に移されることもありますので、忘れないように注意しましょう。
管理費は購入時一括払い
永代供養付きのお墓を購入した時に、管理費も一緒に一括払いすることもあります。
寺院や霊園の決まりで一括払いすることもありますが、施設によっては通常毎年払いのところ、利用する方の希望によって一括払いも可能な場合があります。
これは事前に一括払いをすることで、残される親族などの負担を軽減したいと考える方が多く見られることで対応してくれるケースです。
管理費は不要
永代供養付きのお墓を購入したその後は、管理費の支払いは不要という寺院や霊園もあります。
特に永代供養の合祀墓では管理費不要の場合がほとんどです。管理不要とはいえ管理が行き届いていないというわけではありませんので安心しましょう。
永代供養その後のトラブル事例は?
永代供養付きのお墓を購入したその後に、起こる可能性のあるトラブルの事例は以下の2つです。
- 親族に永代供養を反対される
- 高額な離檀料を請求される
事前にどんなトラブルがあるのかを把握しておくことで、対処しやすくなるでしょう。
親族に永代供養を反対される
永代供養付きのお墓を購入したその後に起きやすいトラブルのひとつが「親族に永代供養を反対される」です。
永代供養は個別供養期間が終了したその後、まったく知らない他の人の遺骨と一緒に合祀されるのが一般的。
しかし親族の中には、血縁者以外が同じ墓に入ることに抵抗を感じるという方もいます。
結果として親族に相談せずに永代供養付きのお墓を購入した場合、親族から大反対されて購入をキャンセルするといったトラブルに発展することも。
このようなトラブルを避けるためには、永代供養付きのお墓を購入する前に必ず親族と話し合うことが大切です。
高額な離檀料を請求される
これまでのお墓を「墓じまいして永代供養付きのお墓を購入する場合、高額な離檀料を請求されるトラブルが多く発生しています。※3
離檀料とはこれまで利用していた寺院などの檀家を辞めるときに、お世話になったお礼として支払うものですが、決められた価格がなく寺院ごとに違います。
トラブルをなるべく避けるためには、これまでお世話になった感謝をしつつも、跡継ぎがいなくてお墓の維持管理ができないことなどをしっかり説明しましょう。
初めから「永代供養付きのお墓を購入します!」と決定事項として話しを進めるのではなく、あくまで悩んでいるから相談したいといった低姿勢で話しを進めることが大切です。
※参考資料:独立行政法人国民生活センター
永代供養その後、法事はする?
永代供養をしたその後、法事をする必要があるのか疑問を持たれる方がいると思います。
永代供養の場合、亡くなられた方のお墓の管理や供養は寺院や霊園がおこなってくれるので、法事をしなくても基本的には問題ありません。
とはいえ、親族で集まって故人を偲びたいと考える方も多いのではないでしょうか。
この場合は法事をおこなうことも可能ですので、寺院や霊園に相談のうえスケジュールなどを決めましょう。
永代供養をしたその後に法事をおこなうタイミングとしては、四十九日や1周忌、初盆などがおすすめです。
永代供養の法事についてはこちらの記事も参考にお読みください
「永代供養」をお願いしたら法事をしなくていいのは本当なの?
法事の費用内訳と相場
永代供養をしたその後に法事をおこなう場合には、以下のことに費用がかかります。
- お布施:約3~5万円
- 会場代:約5,000~3万円
- 会食代:一人約3,000~1万円
- お供え物:約3,000~1万円
自宅などで法事をおこなう場合は、別途お車代もかかります。また、法事に参加する人数や会場の規模によっても費用に違いが出てきます。
法事の服装は準喪服
永代供養をしたその後におこなわれる法事では、特に決められた服装はありませんが、準喪服と同等の服装で参加すると良いでしょう。
正喪服が格式の高い和装の喪服であるのに対して、準喪服とは一般的な喪服のことです。
生き物の死を連想させる革製のカバンや靴は避けるとともに、派手なネイルや化粧も控えた方が良いでしょう。
永代供養その後のお参り方法
永代供養付きのお墓でも、お墓参りをすることは可能です。
永代供養墓の種類によってお参り方法が異なりますので、解説していきます。
- 個別式の永代供養墓
- 集合式の永代供養墓
- 納骨堂の永代供養墓
- 樹木葬の永代供養墓
施設によっては詳細な決まり事がある場合も考えられますので、お参りする前に施設に確認してみると安心です。
個別式の永代供養墓
個別式のお墓は、一般墓と同じように墓石があったり故人の名前入りのプレートなどが設置されていたりします。
個別のスペースが確保されているので、一般墓とおなじような感覚でお参りができます。
集合式の永代供養墓
集合式のお墓は、一か所に多くの方の骨壺を集めて安置してあり、お参りする場所は他の方と共有スペースになっています。
お盆など参拝者が増える時期には混雑も考えられますので、ゆずり合ってお参りすることになります。
納骨堂の永代供養墓
納骨堂にはいくつかの種類があり、お参り方法も種類によって異なります。
ロッカー式の納骨堂であればロッカー前でお参りをしたり、棚式の納骨堂であれば共有のスペースでお参りすることが一般的です。
自動搬送式の納骨堂は施設入口で専用のカードをかざすと、決められた場所に遺骨が搬送されますので、そこでお参りします。
納骨堂によっては、生花不可・火気厳禁などの決まり事がありますので、お参り前には必ず注意事項を確認しておきましょう。
納骨堂が気になる方はこちらも参考にお読みください
納骨堂で永代供養をご検討中の方は必見!必要な費用を詳しく解説
樹木葬の永代供養墓
樹木葬の場合、里山タイプと公園・霊園タイプがあります。公園・霊園タイプであれば、シンボルツリーや故人の名前が入ったプレートの前でお参りすることになります。
食べ物のお供えはお参りした後に持ち帰りが必要な場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
また里山タイプは人の手が入らない自然の中にあることも多く、火気厳禁が基本です。
まとめ
お墓の跡継ぎがいないなどの理由で人気のある永代供養付きのお墓ですが、購入したその後や永代供養されたその後のことを知っておくことで安心して利用することができます。
こちらの記事では永代供養のその後についてまるごと解説してきましたので、もしも永代供養のその後に疑問を感じたときにはぜひ見返して疑問の解決にお役に立ていただければ幸いです。