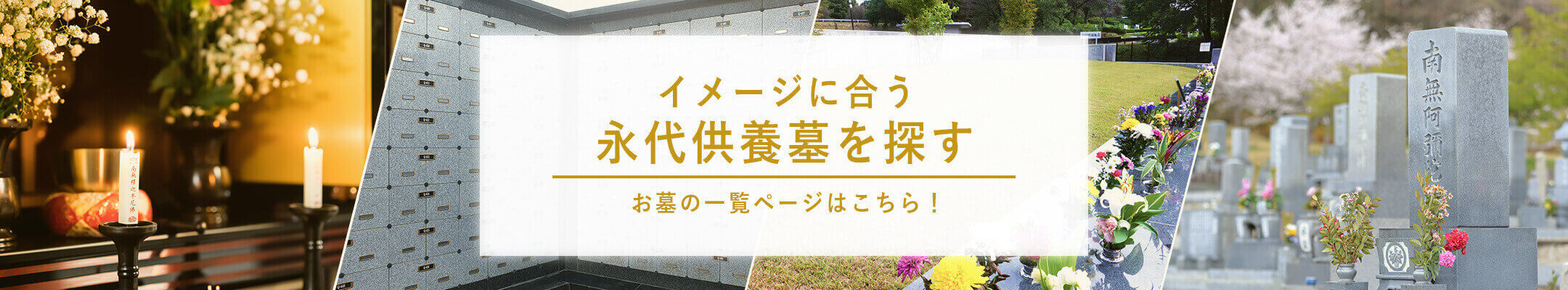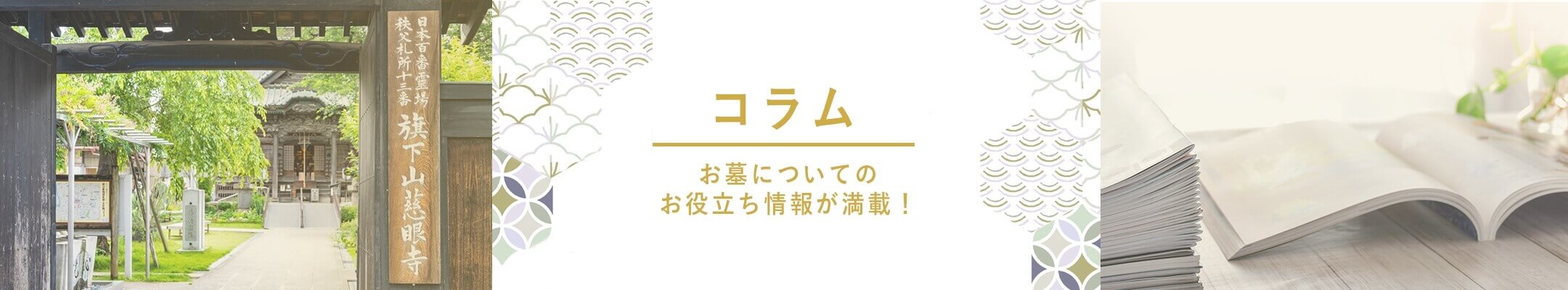永代供養など納骨で必要な埋葬許可証は再発行することができる!
永代供養など納骨で必要な埋葬許可証を紛失してしまったら焦りますよね。でも、大丈夫です。埋葬許可証は再発行することができますよ。
この記事では永代供養などの納骨で必要な埋葬許可証の再発行方法について詳しく説明します。また、埋葬許可証が必要な場面や埋葬許可証の発行方法、永代供養で必要な書類や手続きについてもお話していきます。
永代供養などで必要な埋葬許可証はどうやって再発行するの?
永代供養など納骨で必要な埋葬許可証は大切な書類です。しかし、葬儀や火葬の前後は慌ただしいため、うっかり紛失してしまう方もいらっしゃいます。永代供養など納骨で必要な埋葬許可証は再発行することができます。永代供養など納骨で必要な埋葬許可証の再発行は、火葬から5年以内かどうかで再発行の方法が違います。順に説明していきましょう。
火葬から5年以内に埋葬許可証を再発行する
永代供養など納骨で必要な埋葬許可証の紛失が火葬から5年以内であれば、該当する市役所に行きましょう。市役所では火葬許可証を5年間保管する義務があるため、再発行してもらうことができます。
再発行には印鑑と身分証明書が必要になります。ただし、自治体によって多少手続きが異なることもあるため、埋葬許可証を再発行してもらう前に確認するといいでしょう。
火葬から5年以上経って埋葬許可証を再発行する
永代供養など納骨で必要な埋葬許可証の紛失が、火葬から5年以上経ってしまっている場合は、市役所で再発行してもらうことはできません。再発行には火葬場で発行してもらえる火葬証明書が必要になります。
取得した火葬証明書、印鑑、身分証明書があれば、市役所で埋葬許可証を再発行してもらうことができます。しかし、こちらの手続きも自治体によって手続きが異なる場合があるため、埋葬許可証を再発行する場合は自治体に相談してみましょう。
また埋葬許可証を再発行するために、いきなり火葬場に行っても、火葬証明書の発行に時間がかかるかもしれません。行く前に事前に連絡しておきましょう。また、火葬場を覚えていない場合は葬儀社に確認してみてください。
永代供養など納骨で必要な埋葬許可証とは
そもそも永代供養など納骨で必要な埋葬許可証とは何でしょうか。埋葬許可証とは人が亡くなったときに必要な書類のひとつです。人が亡くなってから火葬や納骨をするにあたって、埋葬許可証以外に、死亡届、火葬許可証などが必要になります。
埋葬許可証について、地域によっては埋葬許可証と火葬許可証が一緒になった「埋火葬許可証」と呼ばれることもあります。近年では人が亡くなったあとほとんど火葬するため、こう呼ばれることが多いようです。
埋葬許可証は故人の遺骨をお墓に埋葬するときに必要な書類です。納骨先に埋葬許可証を提出することで納骨することができます。埋葬許可証という名前ですが、遺骨の埋葬だけではなく、納骨堂でも必要な書類となります。埋葬許可証がないと、埋葬や納骨をすることはできません。
埋葬許可証と火葬許可証の違い
永代供養などの納骨で必要となる埋葬許可証と、火葬許可証は混同されやすいですが、この2つは目的が違います。埋葬許可証は遺骨を永代供養など納骨するのに必要ですが、火葬許可証はご遺体を火葬するのに必要な書類です。
また、火葬許可証は市役所が発行する証明書で、火葬許可証を火葬場で提出して火葬してもらうことで、埋葬許可証を受け取ることができます。永代供養など納骨で必要な埋葬許可証を受け取る流れについては、次に説明しますね。
永代供養など納骨で必要な「埋葬許可証」が必要なとき
永代供養など納骨で必要な埋葬許可証が必要なのは納骨のタイミングです。つまり、お墓に埋葬したり、納骨堂などで永代供養したりするのに必要となります。それ以外では改葬、つまりお墓をうつしたり、墓じまいをするときにも必要となります。
墓じまいや永代供養についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしていてください。
【親の墓がいらない】そんなとき考える墓じまいと永代供養について
つまり、埋葬許可証は一度お墓に納骨しても、のちのち永代供養など墓じまいをすることになった場合、再度必要になります。そのため埋葬許可証は大切に保管しておきましょう。
また、埋葬をせずに手元供養する場合でも埋葬許可証は必要になります。手元供養はすぐに納骨するわけではありませんが、ずっと手元に置いておけるわけではありません。いつかは永代供養など納骨する必要があるでしょう。そのときに埋葬許可証が必要になります。
埋葬許可証の発行方法
永代供養など納骨で必要となる埋葬許可証を受け取る流れについて説明します。
- 市役所で火葬許可証または埋火葬許可証を発行してもらう
- 火葬するときに火葬場へ火葬許可証または埋火葬許可証を提出して火葬してもらう
- 火葬後に火葬をおこなった証明となる認印をもらう
つまり埋葬許可証は火葬許可証に火葬をしたという認印を押してもらったものになります。そのため、自治体によっては始めから埋火葬許可証(まいかそうきょかしょう)と呼んでいるところもあります。
1.市役所で火葬許可証または埋火葬許可証を発行してもらう
ご家族や親族が亡くなったら、医師に死亡診断書を書いてもらい、家族が死亡届を記入します。死亡診断書・死亡届を市役所の窓口に提出しましょう。そのときに、火葬許可申請書にも必要事項を記入して提出することで、火葬許可証を交付してもらえます。
提出する自治体は故人の亡くなった場所、故人の本籍地、または届出人の所在地の市役所になります。火葬許可証には提出期限はありませんが、死亡届は死後7日以内の提出が義務付けられているため注意が必要です。
2.火葬場へ火葬許可証(埋火葬許可証)を提出して火葬してもらう
火葬許可証は火葬をおこなう火葬場の管理事務所に提出します。火葬許可証がないと火葬することができないため、葬儀の日まで大切に保管しておいてください。葬儀当日は、するべきことが多いため、忘れないように最終確認しておきましょう。
3.火葬後に火葬をおこなった証明となる認印をもらう
火葬許可証を提出して火葬してもらうと、火葬済みの認印が押された書類が返されます。この認印が押された書類が埋葬許可証となり、遺骨を永代供養など納骨することができるようになるのです。
埋葬許可証は、火葬後に火葬場の職員によって、骨壺と一緒に渡されます。紛失しないために、埋葬許可証を骨壺の入った箱の中に入れられていることも多いようです。埋葬許可証を紛失したと思ったときには、再発行する前に骨壺の中を確認してみましょう。
埋葬許可証の保管
埋葬許可証は紛失しても再発行することができますが、再発行には時間も手間もかかってしまいます。紛失しないようにしっかり保管しておきましょう。
火葬後に埋葬許可証を受け取るときは、故人が亡くなった悲しみに加えて、葬儀や火葬などの手続きもあり、忙しい状況が予想されます。埋葬許可証の保管場所は、誰かと一緒に確認して覚えておくのがいいと思います。
埋葬許可証が火葬後から必要になるまでは、少し期間があくことがほとんどです。埋葬許可証が必要になるのは、仏教であれば四十九日法要後の納骨や、お墓が完成したとき、また永代供養などの納骨先が決まったときです。
埋葬許可証の再発行にまつわるQ&A
永代供養など納骨で必要な埋葬許可証の再発行にまつわる疑問を解決します。
Q.墓主以外も埋葬許可証の再発行はできるの?
A.埋葬許可証の再発行は、原則墓主か祖父母、両親、子ども、孫がおこなうことになっています。墓主や直系親族が再発行の手続きをできない場合は、委任状を提出して第三者に再発行してもらうことも可能です。委任状には墓主または直系親族の署名が必要になります。
Q.死後数十年後の納骨も埋葬許可証が必要?
A.死後数十年経過したあとであっても納骨には埋葬許可証が必要になります。そのため、手元供養などの場合も、大切に保管しておきましょう。紛失してしまった場合は、再発行しましょう。死後数十年後であれば、まずは市役所に確認したうえで、火葬場で火葬証明書を発行してもらうことになります。
Q.再発行しなくても、埋葬許可証のコピーで納骨はできる?
A.埋葬許可証のコピーを使って納骨することはできません。埋葬時に使用できるのは原本のみになります。コピーしかない場合は再発行してもらいましょう。ただし、健康保険協会などから埋葬料を受け取る書類として使う場合は、再発行せずともコピーで利用できるケースがあります。
Q.郵送でも埋葬許可証は再発行してもらえるの?
A.自治体によっては埋葬許可証の発行や再発行は郵送してもらうことができます。市役所に行くことが困難な場合は、一度確認してみましょう。再発行は5年以内であれば、市役所に火葬許可証が保管されていますが、5年以上経過している場合は、郵送での再発行は難しいでしょう。
永代供養の流れについて
永代供養には埋葬許可証が必要です。では埋葬許可証を使って、どのような流れで永代供養をすすめるのでしょうか。簡単に流れを説明していきます。また、埋葬許可証以外に必要な書類についても説明しますね。
家族や親族と相談する
永代供養をするということは、墓じまいをしなければなりません。すでに墓じまいをしていたら問題ありませんが、これから墓じまいをして永代供養をする場合は、まず親族に相談しましょう。
勝手に墓じまいをすすめるとトラブルに発展しかねません。墓じまいの相談をするときには、お墓に収蔵されている遺骨の新しい供養先や、墓じまいや永代供養の費用についても話し合っておくといいでしょう。
永代供養先を選ぶ
次に永代供養先を決めましょう。永代供養といっても永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨など種類はさまざまです。それぞれの特徴やメリット、デメリットを比較してみましょう。
永代供養の種類について興味のある方はこちらの記事を参考にしてみてください。
永代供養の種類にもよりますが、永代供養先には寺社、霊園などがあります。永代供養の期間や料金、アクセスの良さ、などをポイントに選ぶといいでしょう。また、一般的に永代供養では宗派は問わないことが多いですが、まれに宗派が制限されていることもあるので確認しておきましょう。
永代供養先と契約をする
永代供養先を決めたら契約をします。契約には埋葬許可証と墓主の本人確認書類が必要になります。必要書類は供養先によって違うため、事前に確認して準備しておきましょう。埋葬許可証の再発行には時間がかかる場合もあるため、紛失に気が付いたらなるべく早く再発行の手続きをしてください。
永代供養先と契約するときに永代供養料を支払います。支払い方法も永代供養先によって直接支払いのみのところや、銀行振込やカード払いに対応しているところもあるため、確認しておくといいでしょう。
永代供養料と間違えられる費用として永代使用料があります。永代使用料はお墓の土地を永代にわたって使用するための料金になります。永代供養料はお寺や霊園などで遺骨を預けて永代供養してもらうための初期費用です。
納骨法要をおこなう
永代供養先で納骨するには納骨法要をおこないます。納骨法要には別途お布施が必要となります。ただし、永代供養料に含まれている場合もあるため、確認してみてください。遺骨の一部を手元供養したい場合は、このときに分骨してもらいましょう。
まとめ
- 5年以内に埋葬許可証を再発行する場合は市役所で手続きが可能
- 5年以上経過して埋葬許可証を再発行する場合は火葬場で火葬証明書を発行してもらう
- 永代供養など納骨で必要な埋葬許可証は、火葬許可証(埋火葬許可証)を市役所で受け取り、それを火葬場で提出することで、認印を押してもらって埋葬許可証となる
- 埋葬許可証は骨壺に入っている箱に入れられていることが多いため、再発行する前に確認しておく
- 永代供養は「親族と相談」「永代供養先を選ぶ」「契約する」「法要をおこない納骨する」という流れになる
埋葬許可証は永代供養など納骨で必ず必要な書類になります。埋葬許可証は再発行することも可能ですが、時間がかかる場合もあるため大切に保管しましょう。
「みんなの永代供養」では永代供養やお墓についての情報が充実しています。ぜひ参考にしてみてください。